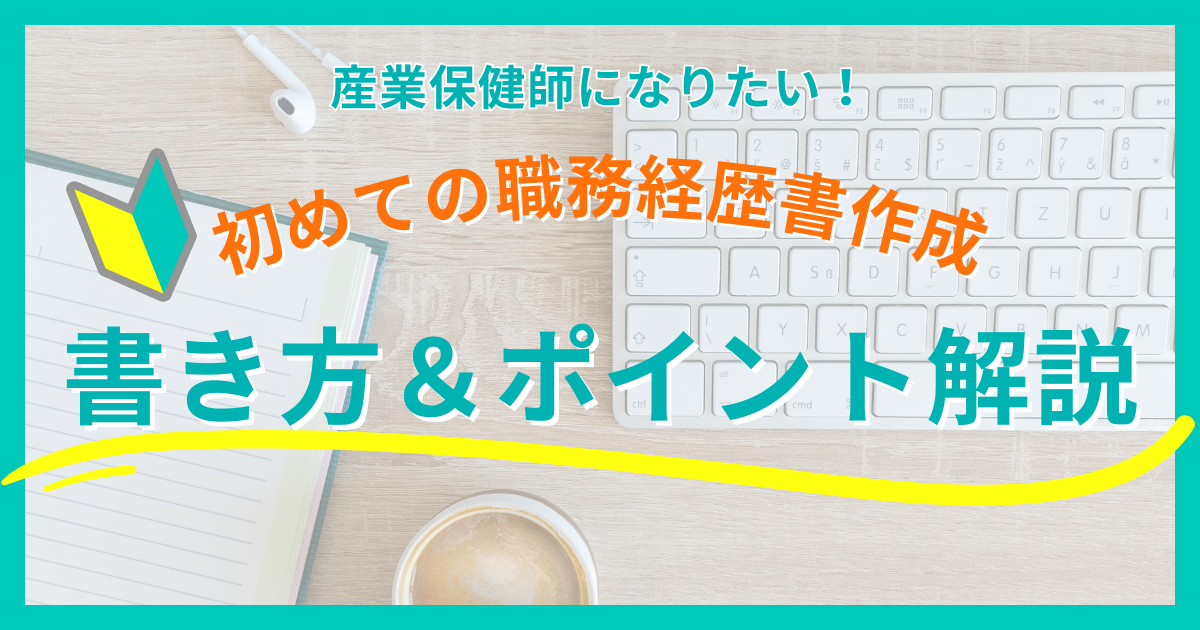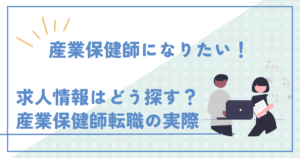こんにちは。独立系産業保健師の きむこ です。
この記事をご覧になっているということは、産業保健師の求人に応募するための書類を準備中 ではないでしょうか?
「産業保健師になりたい!」そう思い、求人に応募しようとしたときに、まず必要になるのが応募書類の作成 です。
特に医療機関や行政で働いてきた方にとって、『履歴書』は馴染みがあっても、『職務経歴書』はどう書けばいいのかわからない… という方も多いのではないでしょうか?
私自身、これまで2回の転職経験があり、その過程で多くの産業保健師求人に応募してきました。幸い、応募した求人の書類選考には一度も落ちたことがありません。
さらに、採用する側の立場として、多くの応募書類をチェックしてきた経験 もあります。
この記事では、産業保健師求人に応募するための『職務経歴書』の書き方を、分かりやすく解説 します。
この記事を読めば、職務経歴書の書き方が分からず不安な方でも、安心して作成にとりかかることができます。
私の転職経験だけでなく、採用担当としての視点も盛り込んでいます。
産業保健師求人に応募する前に、ぜひ最後まで読んでみてください。
産業保健師求人へ応募!必要な書類は?
企業求人の選考では、履歴書や職務経歴書による書類選考が一次選考として行われ、書類選考を通過した人が二次選考(面接)へ進みます。
一般的に、応募時に求められる書類は「履歴書」と「職務経歴書」の2つ です。
これらの書類は、企業が応募者の経歴や適性を判断するための重要な資料 となります。
履歴書は、氏名や連絡先、学歴、職歴、資格などを簡潔にまとめた書類 です。一方、職務経歴書は、これまでの職務経験や実績を詳しく説明する書類 です。
企業は、職務経歴書をもとに、自社が求める経験やスキルを満たしているかを判断 します。
特に、医療機関では応募時に職務経歴書を求められることが少ないため、企業への転職活動で初めて作成する人が多い です。
また、過去に作成経験があっても、「医療機関」と「企業」という異なる環境に向けて書くことに戸惑うケースもあります。
「どんな内容を書けばよいかわからない」と感じるかもしれません。
しかし、職務経歴書の役割や書き方のポイントを押さえれば、誰でも作成できます。
履歴書
履歴書は、応募者の基本情報を伝える書類 です。
氏名、連絡先、学歴、職歴、資格、志望動機などを記載し、企業はこれをもとに応募者の基本的なプロフィールを確認 します。
履歴書は、厚生労働省が推奨する様式があります。(参考:新たな履歴書の様式例の作成について )
特に指定がなければ、厚生労働省が推奨する様式を使用するのが望ましいです。ハローワークインターネットサービスや各都道府県の労働局からダウンロードできます。
手書きよりパソコンを使って作成するのがオススメです。誤字脱字には十分注意して作成しましょう。
履歴書には志望動機の記載欄があることが多いですが、スペースが限られています。そのため、簡潔にまとめることが大切です。
よくある失敗として、具体的な経験やスキルのアピールに文字数を取られ、肝心の「なぜ応募先企業を志望したのか」が曖昧になってしまうケース があります。
履歴書では志望理由を簡潔にまとめ、詳細なアピールは次に解説する職務経歴書で行いましょう。
職務経歴書
職務経歴書は、これまでの職務経験や実績を詳しく伝えるための書類です。
履歴書が応募者の基本情報をまとめたものであるのに対し、職務経歴書では「どのような業務を経験し、どのようなスキルを持っているか」を企業にアピールする ことが目的です。
履歴書がフォーマットが決まっているのに対し、職務経歴書には決まった書式がありません。
そのため、どのように書けばよいのか迷う方も多いですが、応募先の企業が求めるスキルや経験を整理し、伝わりやすい構成にすることが大切 です。
| 履歴書 | 職務経歴書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 基本情報を伝える | 具体的な経験・スキルを伝える |
| 内容 | 氏名、連絡先、学歴、職歴、資格など | 業務内容、スキル、成果、活かせる経験など |
| 書式 | 決まったフォーマットがある | 決まったフォーマットはない |
| ポイント | 正確さ・簡潔さが求められる | 分かりやすさ・アピール力が求められる |
職務経歴書は、単なる経歴の羅列ではなく、「応募先企業でどのように活かせる経験があるのか」を伝えることが大切 です。
履歴書よりも詳しく、「何をしてきたか」「どのような成果を上げたか」「企業にどう貢献できるのか」を明確に記載 しましょう。
次のセクションでは、職務経歴書の具体的な書き方を解説します。
職務経歴の書き方基本の『き』
はじめに│作成する前に確認
職務経歴書を作成する前に、確認し、決めておくべきポイントがあります。
職務経歴書は、「どのような業務を経験し、どのようなスキルを持っているか」を企業にアピールするための書類です。
前提条件を間違えると、企業にマイナスの印象を与えかねません。
職務経歴書には履歴書のような決まったフォーマットがありません。企業によっては指定のフォーマットでの作成を指示する場合があります。
決まったフォーマットがないからこそ、作成ツールや文字サイズ、分量なども、見やすさを考慮して適切に決める事が重要です。
このセクションでは、職務経歴書の基本的な前提条件 について解説します。
作成に入る前に、次の3つの点を確認しておきましょう。
- 指定のフォーマットはあるか
- 作成ツールの選択
- サイズや枚数
次のセクションで、それぞれ詳しく解説します。
フォーマットの指定があるか確認
まずは応募の際に、提出書類のフォーマットの指定があるかどうかを確認しましょう。
転職エージェント経由の場合は担当エージェントに、直接応募の場合は応募要項をしっかりと確認してください。
指定がある場合は、必ず企業の指示に従ってください。
指定されたフォーマットを無視すると、「指示を守れない人」という印象を与える可能性があるため、注意が必要 です。
最近は、紙での提出ではなく、データでの提出や、指定フォームへの入力を求められるケースも増えています。
必ずしも紙での作成・提出とは限らないことに注意 してください。
フォーマットの指定がない場合は、レイアウトや記載内容をすべて自分で決めることになります。
見やすさを意識し、採用担当者がスムーズに内容を理解できるように心がけましょう。
フォーマットの指定があるかどうかで、作成の進め方が変わります。必ず事前に確認しましょう。
作成ツールは?手書き?Word?
職務経歴書は、原則としてWordなどの文書作成ソフトを使用して作成します。
手書きを指定されるケースもゼロではありませんが、Wordなどの文書作成ソフトが普及していることもあり、パソコンで作成するのが一般的です。
文書作成ソフトを使用するメリット
- 修正が容易 → 誤字脱字があってもすぐに修正できる
- 読みやすい → 字に自信がなくても一定のフォントで統一されるため視認性が高い
- データ管理ができる → 複数企業に応募する場合でも、応募先ごとにカスタマイズしやすい
『見やすい書類』を作成するには、ある程度の文書作成ソフトのスキルが求められます。
実際に私が選考する側だった際、職務経歴書が見やすく整理されていると、ある程度のパソコンスキルはありそうだと判断していました。
産業保健師の業務では、書類作成や資料作成など、想像以上にOA作業が多くあります。
そのため、職務経歴書の作成を通じて、文書作成スキルを実例で示すことができる機会にもなります。
手書きの指定がなければ、文書作成ソフトを利用して作成しましょう。
サイズや枚数
職務経歴書は、簡潔かつ分かりやすくまとめることが大切です。
情報を詰め込みすぎると読みにくくなり、逆に少なすぎるとアピール不足になります。
職務経歴書のサイズや枚数は、A4サイズで2枚がベストです。
簡潔にまとまっていれば1枚、経歴や実績が豊富な場合は3枚までが許容範囲です。
選択する枚数毎のポイント
- 1枚 → 簡潔にまとめられていればOK
- 2枚 → 一般的なボリューム、内容が充実していれば適切
- 3枚 → 必要な情報が多い場合のみ(不要な情報を削ることを検討)
応募先企業が求める情報を的確に伝え、読みやすく整理することが必要です。
特に、職務経歴書は「量」よりも「質」 が重視されます。
自己PRや志望動機がメインになっていたり、文書量が多すぎて知りたい情報がすぐに分からない職務経歴書を見ることがありますが、それでは書類選考を通過するのは難しいでしょう。
次のポイントを意識して作成するようにしましょう。
- 情報の取捨選択を行い、不要な内容を省く
- 各項目をバランスよく配置し、適切な分量に調整
- 文字サイズや余白を適切に設定し、読みやすさを確保
次のセクションでは、職務経歴書の具体的な構成と書き方について解説します。
職務経歴書の構成と書き方
一般的な職務経歴書は、タイトル、職務要約、勤務先企業の概要、職務経歴、業務に活かせる知識やスキル、免許・資格、自己PR・志望動機 で構成されます。
各項目ごとに詳しく見ていきましょう。
① タイトル
職務経歴書の冒頭にはこの書類のタイトルである「職務経歴書」と記載します。
企業の採用担当者が書類を整理しやすいよう、ページの一番上に中央寄せで記載するのが一般的 です。
視認性向上のため、タイトルのフォントサイズは通常より大きめ(12pt〜14pt程度)にしましょう。
タイトルに「職務経歴書」以外の表記は不要 です。装飾や余計な文字を加えず、シンプルに記載してください。
タイトルの下に右寄せで作成日と作成者の氏名を入れるのも忘れずに。
② 職務要約
職務要約は、これまでの職務経験を簡潔にまとめ、採用担当者に伝える部分です。
採用担当者が最初に目を通すため、短い文章で「どのような経験をしてきたか」「どんなスキルがあるか」を伝えましょう。
目安は3〜5行程度。
長すぎると読みづらく、短すぎると情報が不足するため、職務経歴の要点を端的にまとめることが大切です。
「端的にまとめる」のが難しいと感じる場合は、次のような流れを意識すると書きやすくなります。
私は〇〇〇で看護師(保健師)として、△△△に携わってきました。その後は□□□で×××の業務を担当しています。
③ 勤務先企業の概要
勤務先企業の概要では、これまで所属していた企業の基本情報を記載します。
採用担当者は、「自社と似た業種ならスムーズに馴染めそう」「この規模の企業経験があるなら心強い」 といった観点で確認します。
記載する項目の例
- 企業名(正式名称)
- 事業内容(業種や主な事業)
- 従業員数(企業規模の目安)
- 勤務期間(入社・退職年月)
企業の詳細な情報は不要なため、簡潔にまとめることを意識しましょう。
転職経験があり、複数の企業に所属していた場合は、時系列で記入しましょう。
医療機関や行政ごとに分ける必要はありません。
④ 職務経歴
この部分は職務経歴書の重要なポイントです。
職務経歴では、これまでの具体的な業務内容を時系列で記載します。
採用担当者は、「どのような業務を経験し、どのようなスキルを持っているのか」 を重視して確認します。
記載する内容の例
- 所属部署名(正式名称)
- 在籍期間(西暦で記載)
- 担当業務の詳細(具体的な業務内容・担当領域)
- 業務の成果や工夫した点の概要(可能な範囲で数値や具体例を交えると効果的)
業務の成果が分かる実績や具体的なエピソードを記載すると、スキルや強みが伝わりやすくなります。
また、転職経験があり、複数の企業での経験がある場合は、所属先ごとに分けて記入しましょう。
こうすることで経歴が時系列で整理され、採用担当者が見やすくなります。
先に説明した「勤務企業の概要」と併せて記載するのが良いでしょう。
⑤ 業務に活かせる知識やスキル
『職務経歴』と併せて、最も重要な部分です。
このセクションでは、業務を通じて身につけた知識やスキルをアピールします。
採用担当者は、「どのようなスキルを持っており、それが自社でどのように活かせるか」 を重視して確認します。
募集要項をよく読み、既に持っているスキルはしっかりアピールし、足りていない部分はポテンシャルがあることを示しましょう。
職務経歴の部分でも業務の成果や工夫点を記載しますが、あくまで概要です。
この部分では、具体的な事例や成果を交えて記載しましょう。スキルの強みがより伝わりやすくなります。
産業保健師の求人で一般的に求められる経験
- 健康診断の運営経験
- 保健指導・面談対応経験
- メンタルヘルス不調者の対応経験
また、コミュニケーション能力や調整力も重要視されるケースが多いです。
応募先企業の業務内容を考慮し、活かせるスキルや経験を適切に選んで記載しましょう。
⑥ 免許・資格
免許・資格には、業務に関連する資格を記載します。
必ず正式名称で記載しましょう。
採用担当者は、「必要な資格を持っているか」「どのような専門性があるか」 を確認します。
看護師・保健師免許の他にも、以下のような資格が該当します。
- 第一種衛生管理者
- メンタルヘルスマネジメント検定
- 両立支援コーディネーター
- 健康経営アドバイザー
なお、第一種衛生管理者は、保健師免許を持っていれば申請のみで取得可能です。
これらの資格以外にも、応募企業の業務内容に関連する資格があれば、明確に伝えましょう。
例えば、事業場間を車で移動する場合は自動車運転免許、工場などで危険物や化学物質を扱う場合は危険物取扱者や作業主任者 が該当します。
⑦ 自己PR・志望動機
自己PR・志望動機では、「なぜこの企業で働きたいのか」「自分の強みをどう活かせるのか」を伝えます。
「産業保健師になりたい」ではなく、「この企業で働きたい」という視点で書くことが大切です。
特に産業保健師の求人では、求人数が少ないこともあり、「産業保健師になりたい」という強い気持ちが裏目に出てしまい、「この企業で働きたい動機」ではなく、「産業保健師として働きたい理由」を書いてしまう人が多いです。
実際には、産業保健師の求人が限られており、選択肢が少ない場合もあるかもしれません。
しかし、それでも企業理念などから共感できる部分を見つけることが大切です。
また、企業の求める人物像と自身の経験・スキルがどのようにマッチするかを示すと、より説得力が増します。
企業サイトに採用ページがある場合は、新卒採用のページも含めてよく読んでみてください。
募集要項だけでは分からなかった企業の求める人物像が、より明確になるはずです。
文書量の関係などから、独立した自己PRや志望動機のセクションがなくても問題ありません。
職務経歴の部分がしっかりと書けていれば、経歴を通してアピールはできているからです。
最後に│最終チェック
誤字や脱字はないか
誤字や脱字は、採用担当者に「注意が足りない」「書類作成が雑」といった印象を与える可能性があります。
作成後は、一度時間をおいてから見直すのが効果的です。
また、パソコンの誤変換や数字の入力ミスにも注意しましょう。
印刷して確認すると、画面上では気づきにくい誤りが見つかることもあります。日を改めて確認するのも効果的です。
必要な情報が網羅されているか
職務経歴書は、採用担当者が応募者の経歴やスキルを判断するための重要な資料です。
内容に抜けがあると、「情報が不足している」「書類の完成度が低い」と判断される可能性があります。
記載漏れしやすいポイントをチェックしましょう。
- 勤務先の正式名称や在籍期間は正しく記載されているか
- 担当業務の具体的な内容が明確に伝わるか
- 免許・資格の名称や取得年が正確に記載されているか
内容に不安があれば、もう一度確認し、必要な情報がすべて含まれているかチェックしましょう。
第三者に確認してもらうのがオススメ
自分で見直しても、誤字や抜け漏れに気づかないことがあります。
そのため、信頼できる第三者に確認してもらうのがおすすめです。
客観的な視点でチェックしてもらうことで、「伝わりにくい表現」「構成のわかりづらさ」 など、自分では気づけなかった改善点が見つかることもあります。
「産業保健師の業務についてなんとなく理解している人」が見ても、内容が伝わる状態がベストです。
添削サービスを活用するのも一つの方法です。
より完成度の高い職務経歴書を作成するために、第三者のフィードバックを積極的に活用しましょう。
これだけは気を付けよう!よくある失敗&注意点3つ
① 「産業保健師になりたい」ではなく「応募先企業で働きたい」を書く
産業保健師として働きたい気持ちは大切ですが、「なぜこの企業なのか」が伝わらなければ、採用担当者の心には響きません。
面接でも、「なぜ産業保健師になったのですか?またはなりたいのですか?」と質問されるケースは多くあります。
これは、医療職=医療機関で働くものという認知バイアスが影響していることが多いです。
そのため、「産業保健師になりたい」だけで終わると、「どの企業でもよいのでは?」と受け取られる可能性があります。
応募企業の業務内容や理念に触れ、「この企業だからこそ働きたい」という理由を明確にしましょう。
例えば、「貴社の○○の取り組みに共感し、自身の経験を活かしたい」といった具体的な動機があると、説得力が増します。
② 自己PRや志望動機が長すぎる
自己PRや志望動機は重要ですが、長すぎると要点が伝わりにくくなります。
特に産業保健師の求人は倍率が高いことが多く、採用担当者は短時間で多くの書類を確認するため、「結局何を伝えたいのか」がすぐに分かることが大切です。
文章のボリュームが熱意として伝わるわけではありません。
同じ内容を繰り返したり、過度に感情的な表現を入れたりしないよう注意しましょう。
簡潔かつ的確に伝えることで、「読みやすい」「ポイントが分かりやすい」職務経歴書になります。
また、自己PRや志望動機のために、職務経歴の記載を削る方がいますが、これは誤りです。
「職務経歴書」という名前の通り、職務経歴から適性を確認するための書類なので、自己PRや志望動機を簡潔にまとめ、職務経歴の中でアピールするのが最善です。
③ 専門用語が多い
職務経歴書は、自分の専門性を伝える大切な書類ですが、専門用語が多すぎると採用担当者に内容が伝わりにくくなります。
特に、人事や経営層など産業保健師の業務に詳しくない人が読む可能性がある ことを意識しましょう。
どうしても専門用語を使う必要がある場合は、以下の点に注意してください。
- 一般的な言葉に言い換えられるものは、できるだけ分かりやすく表現する
- どうしても専門用語が必要な場合は、簡単な補足を入れる
- 略語は初めに正式名称を記載する
採用担当者がスムーズに理解できる書類になっているか、作成後に見直してみましょう。
まとめ
「職務経歴書」の重要性とその作成方法について、履歴書との比較を交えて解説しました。
職務経歴書は、採用担当者に自身の経験やスキルを伝え、選考を突破するための重要な書類です。
そのため、簡潔で分かりやすく、読みやすい構成を意識して作成しましょう。
採用担当者が知りたいのは、「どんな経験やスキルを持っていて、それが応募企業でどのように活かせるのか」 という点です。
しかし、「産業保健師になりたい気持ち」を書くことに意識が向きすぎてしまったり、自己PRや志望動機が長くなりすぎたりすることで、書類の魅力が半減してしまうケースも少なくありません。
また、企業ごとに求められる役割は異なるため、一度作成した職務経歴書をそのまま使い回すのはNGです。
応募企業ごとに見直し、適切にアピールできているかを確認しましょう。
職務経歴書は、一度書いて終わりではありません。
読み手の視点を意識しながらブラッシュアップを重ねることで、より伝わりやすく、説得力のある書類になります。
焦らず丁寧に仕上げ、あなたの経験やスキルを最大限に活かせる職務経歴書を作成しましょう!